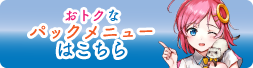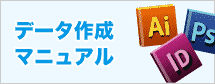HOME > コラム > その原稿は大丈夫?RGBとCMYKの違い
その原稿は大丈夫?RGBとCMYKの違い
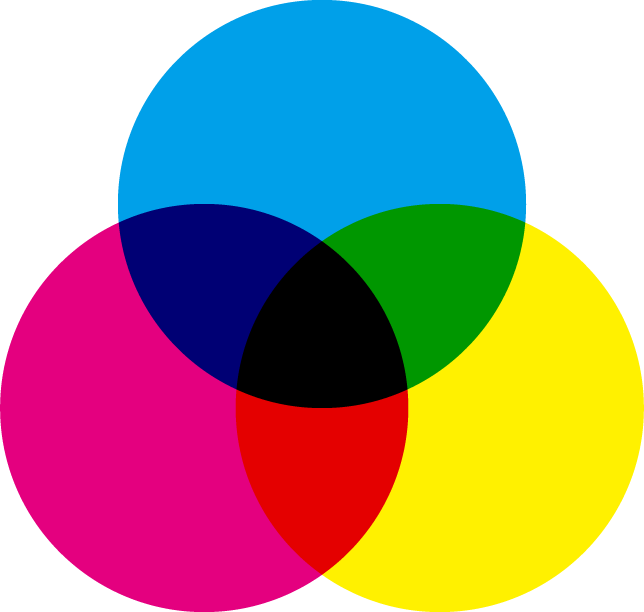
こんにちは!福田です(^^)
「CMYKで入稿してください」と書いてある印刷会社さん、多いですよね。
同人プリント!もそうなんですが、なんでCMYK固定なの(*´Д`)?って思うことありませんか?
今回は、そんなCMYKとRGBについて、お話していこうと思います♪
光の三原色 RGB
RGBとは、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の三原色のことです。
発光によって見える色で、混ざると白に近づいていく加法混色です。
なので、赤、緑、青を混ぜると、あら不思議!色がなくなってしまうのです!!
小さい頃、栃木県宇都宮市に体験型の博物館があり、そこで実際に光の三原色を混ぜて、
とても驚いた覚えがあります!
絵の具で色を混ぜたら、だんだん汚い色になっていって、混ぜまくってると黒になってしまう
…というイメージがあったので、かなりビックリしました(笑)
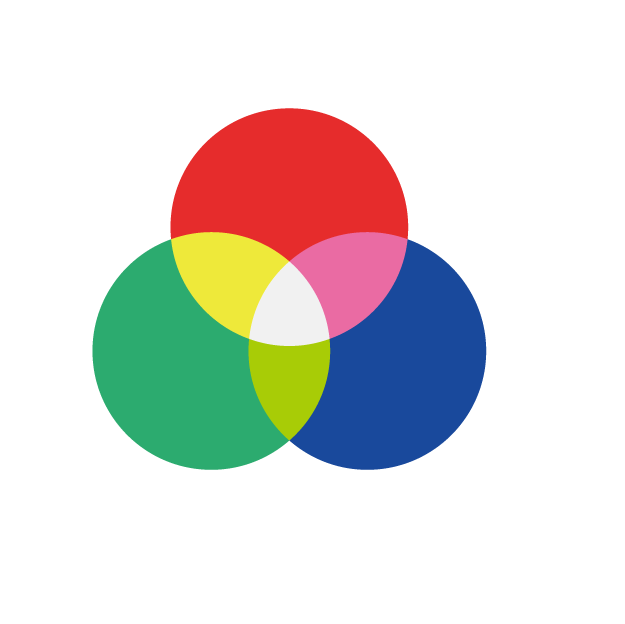
光なので、重ねれば重ねるほど、明るくなっていくのが特徴です。
パソコンのモニターやテレビなどに使われている表現法です。
色材の三原色 CMYK
まずC,M,Y,Kと4つ書いてあるのに三原色!?って思いませんか?(笑)
実は、C(青緑/Cyan)、M(赤紫/magenta)、Y(黄色/Yellow)の三色が、三原色と
なっています。
色を混ぜ合わせていくと、光のエネルギーが減少し暗くなります。
これを減法混色といいます。
えっ!?Kどこ行っちゃったの?ってなりますよね。
この三原色を混ぜ続けると、黒になる…のですが、実際のインクでは理想的な反射特性には
なっていないために、3色を合わせ続けても黒にはならず、暗い茶色止まりになってしまう
んですねー。
なので、ここにK(黒/Key tone)インクを追加して、4色構成になるのです。
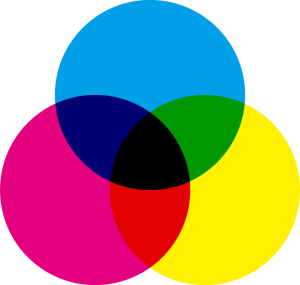
印刷物は、このCMYKで表現します。
光の三原色と色材の三原色の差
光で明るく表現される「光の三原色」と、混ぜれば混ぜるほど暗くなっていく「色材の三原色」。
写真やパソコンで作った書類、ペイントソフトで描いたイラストなども、だいたいRGBモード
になっていることが多いです。
画面上は明るく見えますが、実際印刷してみたら色が濁っている!と思われたことは
ありませんか?
RGBよりもCMYKの方が表現できる色の領域が狭いために、色が変換されて落ち着いた色合いに
なってしまうんです。
画面の色と印刷物の色合いが違うときには、RGBモードかCMYKモードかを確認してみましょう♪
おわりに
RGBで表現できる色は16,777,216通りもあるそうで、そりゃCMYKで表現出来ない色あるよねー
と思いました(笑)
RGBは光で表現しているため、光がないと真っ黒になってしまうそうです。
テレビを消すと真っ黒になるのがいい例で、光によって色を表現しているところ、電源を落として
光を遮断すると色が見えなくなってしまう…という仕組みなんですね!
考えた人、すごい!!
ということで、RGBとCMYKの違い、分かりましたか?
印刷用データはCMYKで作成しましょう♪
この記事のトラックバック用URL
関連記事一覧
single.php